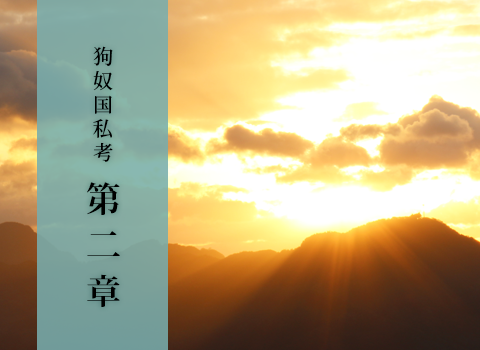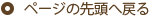目次
 第二章
第二章
邪馬台国の卑弥呼と天照大神
国譲り前の出雲の
大國主命と少名毘古那神
「台与の邪馬台国」の北部にあたる北九州市から遠賀川流域にかけては、不弥国にあたり、弥生後期の遺跡から遺物が多数出土している。また、鉄製の槍鉋も多数出土するようであり、木造船の建造に使われたと想定されている。それが、出雲平定に向かった天鳥船であり、河内に向かった饒速日の天磐船ではないかとする説がある(安本美典『最新邪馬台国論争』)。私もこの見解に賛同する。
遠賀潟流域で作られた小船に乗って本州島の出雲国に渡ったのが少名毘古那(少彦名)であった。『記』は記す「大穴牟遅命(おほなむじ=大國主)が出雲の御大之御前にいた時、波の彼方から天之羅摩船(図9)に乗って、鵝皮をすっかり剥いで衣服とし、小さな船に乗って寄って来る神がいた。

のガガイモの実
このように数々の最先端技術を葦原中国(四国島を含む)にもたらした少名毘古那は、海を渡ってきたが来たが故に、三韓半島からの渡来人とする意見もある。しかしそれは断じてありえない。その証拠が温泉療法、醸造技術、虫送りである。天然湧出の温泉は、活火山のない半島には無い。温泉療法は温泉が多い九州島の邪馬台国連合の人々の知恵とすべきである。醸造技術では、神功皇后が、誉田別皇子(応神天皇)の禊後の都への帰還に際し、待酒を少名御神が醸した酒として楽しんでいる。『魏志倭人伝』は「人性嗜酒」と記し、日本人は古来酒を楽しんでいた。米麹カビと酵母で造る酒であれば、米麹のアスペルギルス オリゼは日本に普遍的に存在する。本カビは猛毒のアフラトキシンを作る遺伝子を欠いており、醸造には最適である。たとえ、かみ酒(米を噛んで酒槽に吐き入れて醗酵させる)であっても、日本古来である(『紀』木花開耶姫条、『大隅國風土記』逸文)。
虫送りにしても、水稲のない半島では考案されない技である。『三国史記』百済本紀は、「多婁王六年(33年)二月 下令國南州郡 始作稲田」とあり、この時初めて陸稲栽培が始まったと解される。「田」は「畑」を示すからである。『三国史記』新羅本紀は、悲惨な食糧状況を記す。例えば、「奈解尼師今十一年(122年)秋七月、飛蝗害穀、年饑多盗」。「逸聖尼師今六年(139年)秋七月、隕霜殺菽」。「奈解尼師今二十七年(222年)夏四月、雹傷菽麦」。菽(豆類)と麦は記されるが、稲は無い。害虫防除も無い。水稲栽培や害虫防除は、当時の半島には無いとすべきである。夏に水稲を荒らす害虫をはらう「虫送り」は九州で発達したと考えるのが妥当である。米酒の醸造や温泉療法などを伝授したとされる渡海の少名毘古那は絶対に半島からの渡来人ではありえないのだ。九州北部海域には対馬海流が流れている。 この流れに乗れば小舟でも容易く出雲にたどり着ける。例えば、「山陰から北海道に掛けての日本海に面した内陸側沿岸域では、いずれの海岸域でも日本製ゴミの漂着が高く、数量的に外国製ゴミを上回っている」(「漂着ゴミの産出発生源と漂流漂着ルートの推察」Web)との最近のデーターも、これを支持する。出雲に船で現れた少名毘古那は、九州島北部から小舟で出雲国に来たとするのが理に合う。以上の理由から大穴牟遅のいる出雲国に船で現れた少名毘古那は、九州島北部から小舟で来た倭人の賢者であったとするのが合理的なのだ。その少名毘古那神は福岡県北九州市の遠賀川近くの岡田宮に祀られている。少名毘古那が帰った常世郷とは少名毘古那の生まれ故郷(不弥国)といえよう。