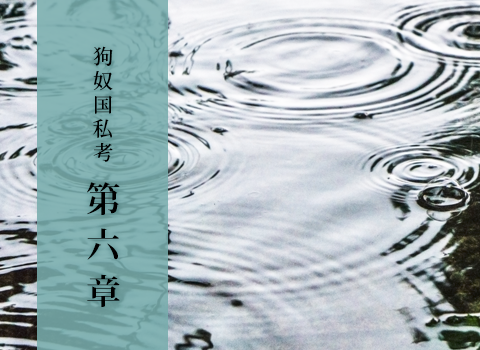目次
 第六章
第六章
狗奴国王統の盛衰
十一代垂仁天皇
(2)もの言わぬ誉津別皇子
もう一つ狭穂姫にまつわる説話である、誉津別皇子(ほむつわけのみこ)を論考してみよう。垂仁天皇は、狭穂姫の遺児の誉津別皇子をこよなく愛したが、皇子には発話障害があった。垂仁二十三年、生まれて三十歳になるまで、言葉を発しなかった皇子が、鵠(白鳥)を観て、「是何者ぞ」と初めて言葉を発した。その後、「出雲大神(大國主)」を参拝して、言葉を話す様になる。言葉を発しない皇子を『記紀』の解説は「唖」とする。また、天智天皇の御子の建皇子が唖であったことを取り上げ、誉津別皇子の物語は、天智朝の建皇子の物語のコピーであるかのように解説する。しかしながら、誉津別皇子を医学的に観れば、「聾唖」ではなく「失声症」と診断できる。なぜなら、成長して意味ある言葉を発しているからである。つまり、「聾唖」と異なり、聴覚障害が無いことがわかる。『紀』に基づけば、誉津別皇子は二、三歳の時、母の狭穂姫が燃え盛る稲城の中で焼死するのを目撃した。子供にして「声を失う」ほどのショックを覚えたはずである。心因性ショックにより「失声症」になったのだ。いかに天皇が愛重もうとも、母を焼き殺した張本人と暮らしていては皇子のトラウマは癒えるはずがない。大人になり、天皇と離れ、出雲大神を詣でる旅行をしてストレスが緩解したことで「失声症」が緩解したのである。『記』が、皇子の失声症を「出雲大神(大國主)の祟り」のように記すのは、時代的に当然のことである。反面、どうも、医学の知識に乏しい文系の学者(上田正昭、吉井巌、次田真幸など)の研究は、事象を誤解釈して、日本の古代史をあらぬように歪曲しているようにみえる。また、皇子の道行きの占や誓約(うけい)に現れる超常現象は、結果を「吉・可・善し」としたい人間の願望を表したものとみるべきである。超常現象をもって、誉津別皇子の実在を否定するのも、いかがなものか。
*誉津別皇子の出雲詣での帰路における、肥長比売の逸話を『記』が記す。
皇子は、出雲詣での帰路、美人の肥長比売と一宿の婚をもつが、比売を伺うと、正体は蛇(おろち)であり、皇子は大慌てで遁走する。船で逃げる皇子一行を蛇(比売)は海原を光らして追いかけてくる。皇子一行は山のたわで船を捨てて逃げ上り、蛇から逃れることができた。
短い話であるが、逸話には真実が語られていると私は主張してきた。蛇が美女に化けるわけがない。おそらく肥長比売は「腋臭、すそわきが」を持っていたのであろう。初めて女性体験で、その強烈な異臭を感じた誉津別皇子は、古来、蛇の吐息は生臭いとされていたので、比売の正体を蛇と覚えたのである。それで、逃げだした。肥長比売は貴人の落胤がほしくて後を追った。皇子一行は船に乗って逃げるが、海には夜光虫が発生しており、船の櫓が作る波の刺激を受けて夜光虫が発光した。皇子には、光る長い航跡を、比売が「光る蛇」となって追いかけて来るように見えたのだ。上陸すれば、それ以上、海原は光らないので、皇子は「光る蛇」から逃れたと覚えたのである。この逸話は、舎人が執筆をした『紀』は載せていないので、女性の生理がわかる猿女君の脚色であろう。この逸話が、なぜ「聖婚への過程」をものがたる(吉井巌)と解釈できるのか、私には理解できない。
文系の先学は、誉津別皇子の説話を、農耕祭儀をうかがわせる神秘的な出生、奇跡の回生(発話障害の緩解)および聖婚(蛇姫との婚い)と論考する(松前健、三品彰英、吉井巌)。しかしながら、母親が焼死する戦火から救出された皇子の半生を、上記のように医学や生物学の知見をもって考察すれば、神秘的な出来事はなにもないといえよう。